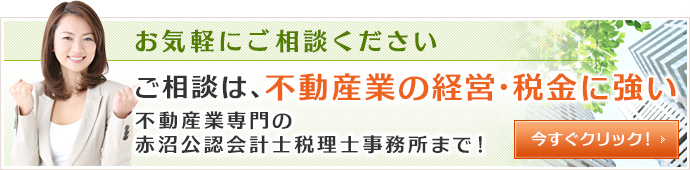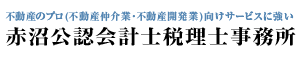旅費規程と出張手当
もし遠方の出張が時々生じるのであれば、旅費規程を作成した上で規程に基づき出張手当を本人に支給することで、本人に現金を無税で支給することができます。つまり本来現金を社長や社員に支給しますと貰った個人には給与を貰ったのと同じように所得税住民税がかかります。
しかし旅費規程を作成し、旅費規程の中で「社長に対し日帰り出張で1万円、出張の一泊につき2万円支給等々」と設定しますと、規程通りに現金を支給しても本人には所得税住民税はかかりません。それでいてもちろん法人の経理になります。
交通費宿泊費等と別途精算する必要もなく、交通費宿泊費等は領収書に基づいて実費で経費化することができ、本人が立替えたのであれば法人から精算時に支給していただいて結構です。
金額を常識の範囲内で設定していただければ問題はありません。
関係会社の活用
法人に安定してある程度大きな利益が出ている場合に有効な方法です。
現在の法人以外に別の法人を設立します。
主たる法人をA法人とし、別の新法人をB法人とします。
A法人からB法人に様々な運営サービスを委託し、業務委託料をA法人からB法人へ支払うことで、利益の出ているA法人が業務委託料分だけ利益を圧縮することができます。B法人では業務委託料分だけの売上を上げます。
A法人が最大実効税率33%が適用される所得800万円超であれば、B法人への業務委託料のおかげで所得を圧縮し、より低い21~23%の実効税率の適用を受けることで法人税等の負担を大幅に減らすことができます。
その際の業務委託内容としましては、経理業務の代行、請求管理業務の代行、財務管理業務の代行等が一般的です。
なお業務委託料の金額は世間及び業界の常識的な線で設定する必要があります。
あまり多額の場合には税務署に否認される危険がありますので注意する必要があります。
経費の損金算入一般
個人事業と法人とでは税金計算上の経費の範囲に違いがあります。
個人事業の方が極めて狭く厳格です。結果的に法人の方が経費として認められやすいということです。
例えば自家用車を業務用として使用している場合、個人事業では全額を事業経費として参入することは認められません。
いくらかは必ず個人的な使用がある筈だから、100パーセント経費にするのは駄目と税務署から指摘されます。
しかし法人名義の車両もしくは、法人が個人から借り上げてるかたちになっていれば、全て法人で事業として使用しているという前提になります。もちろん明らかに個人の使用が判明すればその分はいくらか経費算入を控える手立てが必要になります。
また個人事業では、現に行っている事業に直接的に必要な経費しか経費として認められません。個人で不動産業を営んでいれば、その不動産業に関係するセミナーや研修の経費は認められますが、不動産業と異なるネット販売や財務投資に関わるセミナー研修等の費用は認められません。
しかしこれが法人であれば、現に営んでいるのが不動産業ではあっても、ネット販売や財務投資に関わるセミナー研修費用が経費として参入できます。
法人経営では、現に営んでいる不動産業だけではなく、今後の新ビジネスとしてネット販売や財務投資の研究開発に支出するというのは特別なことでなく、通常の事業活動として認められることになります。
もちろん法人名義の領収書・請求書が必要です。
減価償却の計上が任意
建物・付属設備・構築物・機械装置・車両・器具備品等のいわゆる固定資産については、固定資産の細かい種類毎に定められている耐用年数に渡って少しづつ経費に算入していきます。いわゆる減価償却と言う経理処理です。
例えば500万円の車両を購入してもその年に一度に500万円全額を経費算入することはできず、耐用年数6年に渡り分割して経費に算入していきます。その分割の仕方には毎年同じ金額を経費算入する定額法と前年の償却をした後の残額に一定な償却率を乗じる定率法等の方法があり、どちらかを選択することができます。
定額法であれば1年目から毎年約83万円の一定額を経費算入しますが、定率法であれば、1年目に約166万円、2年目に約111万円、3年目に約74万円と言ったように段々と償却額が小さくなる計算になります。
さてここまでは個人事業も法人も同じです。
違うのは、個人事業ではこの計算に従って減価償却費の計上が強制されるのに対し、法人では減価償却費の計上の任意だということです。
つまり車両の減価償却費を計算上83万円計上するとなった時、個人事業では必ず83万円を申告書に載せなければなりません。もしわざと空欄にして申告書に記載しなくとも、税務署は減価償却費83万円を計上済みだとみなします。
一方、法人の場合には、この最大83万円まで計上できる減価償却費をフルに83万円計上しても良いし、半分の41万円だけにしたり10%の8万円だけにしたり、一層ゼロにして全く計上しないという選択もできるということです。
不思議なようですが、法人は経営上合理的な減価償却の計算を自主的にできるという前提で税務署も対応しますので、その対象資産の使用状況を最もよく認識している法人の判断を尊重するという形になっています。
このために個人では減価償却費の計上額を選択することはできませんが、法人ではその時の損益状況によって減価償却費の計上額を調整することができるということになります。そうなりますと利益が大幅に出ている年度は減価償却費を最大限計上して税金を抑制し、赤字気味の年度では減価償却費を最低限度だけしか計上せずに赤字幅を減らすこともできます。
法人では所得400万円超より税率が上がりますので、これらの調整により所得及び税金を抑制することもできます。